
資料:厚生労働省
上の表をご覧ください。
少し前の厚生労働省資料ですが、先進各国の医療提供体制について比較したものです。
赤い丸で囲まれた数字を見てください。
日本の人口1000人あたりのベッドの数、つまり入院することができる数は先進各国の倍ほどの数がありアメリカの4倍以上となっています。
ですが患者100人当たりの医師や看護師の数は半分以下でアメリカの4分の1程度しかいません。
2021年5月発表時点での新型コロナの新規感染者数はアメリカで34.493人(8日)イギリスで1770人(9日)ドイツに至っては未だに13,125人の感染者数がありますが医療崩壊はしていません。
日本は2021年5月10日の時点で新規感染者が6,492人、重傷者数は1,144人となっています。ですが日本では救急搬送が必要な患者の受け入れ先がないなど、すでに医療崩壊といっても過言ではない状態へと陥っています。
もちろん先進各国のと比較して人口比率の問題やワクチン未接種などの問題もありますがこの医療崩壊は現在の感染者数に至る以前から起きていました。
昨年2020年5月頃を思い出してください。入院先がなく自宅療養中であった方が急変して亡くなった。等のニュースが飛び交っていたと思います。現在も同様の状態です。
今この日本でなぜ医療崩壊が起きているのでしょうか。
日本の医療提供体制についてわかりやすく説明します。
医療供給制度とは
医療政策・医療制度を語るうえでまず最初に考えなければならないのが医療の費用をどのように負担するかという問題です。
そしてもうひとつ重要な問題が医療を提供する体制をどのようにつくっていくのかということです。
医療は一般の需要のように放っておいても商売をする人が出てきて買いたい人がいれば買えば良いというように市場で全てが成り立っていくというものであってはなりません。
もしそこに政策が関与せず
放っておくと儲かる都心部にどんどん医療施設ができて過疎地には医療体制がないという問題が出てきてしまう恐れがあります。あるいはいい加減なものがどんどん出てきてしまうと医療どころか逆に病気になってしまう可能性もあります。
なので一定の規制を設ける必要があります。これが医療供給の内容となります。
医療制度にかかる費用、保険料に関してはこちらをご参照ください。
医療を提供するところ
私たちが医療を受けるところ、医療が提供されるところはどのようなところなのでしょうか。
わたしたちが病気になった場合に医療を受けるところは制度上病院と診療所となります。
法律上はこの病院と診療所が医療を提供するということになっています。
したがってそれ以外のところでは継続して医療を提供することはできません。
そして病院と診療所で医療を提供するにはこれだけの体制を整えなければならないということが法律で決められています。
病院と診療所の違い
- 病院:20床以上
- 診療所(クリニック):19床以下、または病床なし
まず病院として認定されるところはベッドが20個以上ある施設となります。
そして診療所はベッドの数が19個以下や入院する設備がないところをいいます。
多くの診療所(クリニック)では入院設備のないところがほとんどです。
ということで病院と診療所の違いはなんとなく大きいところと小さいところという分け方になってはいますが、それぞれの持っている機能が異なります。
病院の区分
病院とひとくくりにいってもいくつかの区分に分けられています。
病院のなかで一定の役割をもつ病院がまずピックアップされています。
- そのひとつが特定機能病院です。
- そしてもうひとつが地域支援病院です。
これらは一般の病院とは違う要件(人員配置や設備構造の基準、管理者の役割など)で運営され役割が明確になっています。
これ以外には精神病院や結核病院といったような特定の病気に対応する病院があります。
これら以外は全て一般病院というくくりになっています。
まず特定機能病院とはどういうものなのでしょうか。特定機能病院とは高度な医療ができる病院のことを指します。高度な医療を提供する、高度な医療技術を開発する、あるいは高度な医療に関する研修を実施するという役割をもっていてそれができる病院のことをいいます。
基本的には大学病院や国家公立病院の大型の病院があたります。
この特定機能病院は厚生労働大臣が個別に指定をすることになっています。
2019年4月時点で全国に指定を受けた特定機能病院は86病院あります。
これは承認されたらそれで良いかというとそういうわけではありません。医療過誤事件が発生したり設備向上をおこたり設備が古くなり使い物にならなくなった…などの事態が起きるとこの特定機能病院の承認を取り消されてしまいます。
近年では主に医療過誤ということで群馬大学の医学部の附属病院と東京女子医大病院が2005年に承認を取り消されています。
いっぽう地域支援病院とはどのような役割なのでしょうか。
地域医療をささえるのは「かかりつけ医」だということでこの「かかりつけ医」を支援する病院として地域支援病院は存在しています。
「かかりつけ医」から紹介を受けて検査や手術をする,
というように「かかりつけ医」と連携してより高度な医療を提供する病院となっています。
こちらは都道府県知事が指定をするというかたちになっています。
これらの他の病院の区分としては病院ごとの区分ではなく病床ごとの区分があります。
こちらは病室ごとやフロアごとの区分となります。この区分ではフロアごとの職員配置など提供する医療の内容によって基準が異なっています。
区分としては精神病棟、結核病棟、感染症病棟などのようにフロアや部屋ごとに異なった基準が設けられています。
さらに病院内で診療報酬も分けられています。1日入院するといくらという入院管理料は疾患によって人員配置が異なるため金額が異なっています。
これは医療提供体制の法律で決まっているわけではなく、診療報酬で区分されています。
DPCの病院や地域包括ケア病棟などのようなかたちで区分されています。
このようなかたちで色々な観点から病院は区分されています。
このうち一番細かく病院を区分しているのが診療報酬です。
これは本来としてはおかしな話なので病院の機能によってきちんと区別していかないと役割としてきっちり機能しないことにもつながります。
特にこの区分によって急性期の重篤な患者を診る病院と慢性期や回復期の患者を診る病院とがしっかりと区分されずにごちゃごちゃになっているのが現状です。
診療報酬上は区別されていますが機能としての区別が曖昧で、現在の日本には「その他一般病院」というのがたくさんある状態です。
病院の役割や機能を明確にしていこうという動きもありますが、ただ病院側から根強い抵抗・反対がありなかなか実現していません。
もうひとつの問題が配置が不均衡となっているということです。その中でも
特に大きな問題として言われているのが病院に長く入院し続けているということです。
これは配置が不均衡であるため長期入院の病院が固まっているという状況になっているということです。病院からなかなか退院できない、しないということは結局病院の経営のためにベッドを埋めているという事態が起こっているのではないかということが一部で議論されています。
日本の医療提供体制の特徴

資料:厚生労働省
出典:OECD Health Data 2015・2014・2013・2012
- ※1:2012年の数値データ
- ※2:2011年の数値データ
- ※3:2010年の数値データ
- #:実際に臨床にあたる職員に加え研究機関等で勤務する職員を含む
- 病床100床あたりの臨床医師数ならびに臨床看護職員数は総臨床医師数を病床数で単純に割って100をかけた数値である
- 平均在院日数のカッコ書きは急性期病床(日本は一般病床)における平均在院日数である
上の表は少し古いデータですが日本の医療提供体制がわかりやすく表されています。
各国と比較して一目でわかるのは青い丸で囲まれた平均在院日数です。
他の先進国と比較すると3倍以上になっています。
そして病床当たりの医療従事者の配置が極端に少ないことがわかると思います。
しかし、人口当たりをみるとさほど少ないわけではありません。
つまり病院全体でみれば人手不足で大変だということはありませんが、病床当たりにしてみるとかなりの人手不足となっています。
なぜこのようなことが起きているのでしょうか。それは病床が多いからです。そして病床が多いから長く入院している、というかたちになってしまっているのではないかということが考えられます。
日本の医療費というのはそれほど世界に比べて高いわけではありません。
ですがじわじわと上がってきているのは事実です。
入院期間が長いということは結局医療機関に入院すれば医療費が余分にかかるので医療費の無駄使いなのではないかという意見が一部ではあります。
病気は治っている、また治りつつあるような人でもなんらかの事情によって家に帰ることができない。このために病院に入院し続けている人たちが多くいます。
これは医療費の無駄遣いだけでなく本人にとっても良いことではないのではないかということで医療的に入院が必要ではないにも関わらず入院している人のことを社会的入院
と呼んでいます。
わが国では社会的入院を減らして平均在院日数を短くしようとするという政策による取り組みが長きにわたっておこなわれてきています。
ですが実際のところはなかなか上手くいっていないという現状があります。
上の表の数字の取り方には様々な意見があり定義の変更もありました。直近のデータでは数字自体はは減っていますが定義が変わっているため、現実的に長期入院が減ったかというとそうではありません。
したがって政策の効果は実はあまり上がっていないということが示唆されます。
ではなぜ日本は長期入院がまん延する国になってしまったのでしょうか。
その背景には疾病構造の変化があります。
疾病構造の変化と医療体制
日本が医療を広く多くの人に行き渡るように普及させていかなければならなかった時代は感染症のまん延が中心だった時代でした。
その勢いがその後も続きますが、感染症というのは外から悪いものがやってくるということで病気になるということは本人が悪いから病気になっているということではありません。
たまたま運が悪くウイルスや菌に感染してしまい病気になります。
そして病気になると他のひとに移してしまう可能性があるので早く見つけて早く治す、そして他の人に移さないように入院して集中的に治療するということが当時の医療のかたちでした。
そして医療保険も感染症中心の時代につくられたものです。病気は本人の責任ではないので早期に医療を受けられるようにしなければならない。そしてお金がないから医療を受けることができないということにならないように病院に行きやすくしなければならない。というのが医療保険の最大の役割でした。
このような考え方のもとに医療供給体制も医療費の給付の制度も整えられていきました。
ところが時代とともに感染症は徐々に少なくなっていきます。
そしてそれに代わって疾病の中心となってきたのが心疾患、糖尿病、脳卒中などの生活習慣病でした。
こういった病気は感染症のように外から悪いものが入ってきて病気になるわけではなく、自分の身体のなかで悪いものを育てていき病気になるというかたちです。
このような病気が主になってくると病気になったのはたまたま不幸だったというわけではなく、生活習慣のなせる業でありいわば自業自得という考え方がされるようになってきました。
そして疾病自体にも変化が生じ、早期に発見して早期に集中的に治療をすれば元通りになるというわけにはなかなかいかなくなり、いつまでも長引きなかなか完治しない病気が多くなりました。また1つの病気がまた新たな病気を引き起こすというように変化をしてきました。
そして現在のように治療を続けながら生活を続けるという時代へと変化しました。
そうなってくると感染症中心の時代につくられてきた医療提供体制は現在の生活習慣病中心の時代ではちがったものとならなければなりません。
ところが一旦つくってしまうとそこに多額の費用が投入されているため、急に変えることができないという面があり、医療提供体制はなかなか変わらないという問題があります。
入院して集中して治療をおこなうという体制でつくった病院に長々と治らない人が入ってきていくら治療をしても治らないということになればいつまでたっても退院しないということになります。
そこでいくらベッドを増やしても入院患者は入ってきて退院しないためどんどんベッドが足りなくなるという状態に陥ります。
これ以上集中的に治療をしても回復しないのであれば慢性期やリハビリなどは病院以外の別の施設で提供する、あるいは自宅から通院するというかたちに変えていかなければなりません。
ですがなかなか病院の体制も患者側の認識も変わらないというのがいまの現状です。
長期入院がもたらすわが国への影響
このようなことが結局,医療提供体制が時代に合わないという現状をつくってきてしまいました。
これは医療保険でも同じようなかたちになってきており、特に高齢者に長く病気が治らない人が多くなっています。
生活習慣が積み重ねられてくると病気になるのは高齢期になってからです。そして治らないということになると結局高齢者が多く医療費をつかうということになります。
本来「保険」は誰がいつ病気になるかわからないのでみんなでリスクを分散しましょうというかたちで成り立っています。ですが実態としては病気のひとはいつまででも病気で病気にならない若い人はほとんど医療費をつかわないという状態となっています。
ということで特定のひとから特定のひとにお金が流れていく仕組みになってしまっています。しかもそれが感染症のようにたまたまではなく自業自得ということになると、なんで自分だけがお金を払わなければならないのかという意識がだんだん強くなってきます。
かつて人工透析は自分の責任だといって大きな批判を浴びた元アナウンサーがいました。
このように若い人と高齢者の間にある意味一体感がなくなってくるというようなことが起こってきたのは現代の「疾病構造の変化」に制度がうまく対応していないからといって過言ではありません。
長期入院に対する政策
このようなことで長期に渡って医療を受けながら、病気のために退院して生活が十分うまくできない人が多く存在します。このような人たちが家で生活するという体制ができていないために結局ずっと入院し続けているというわけです。
これが長期入院の1つの要因となっています。医療は医療だけのはなしではなく、介護やその他の生活支援と一体となって考えていかないとこの長期入院という問題は解決しません。これが現在さかんに叫ばれている地域包括ケアにつながっているわけです。
とはいいつつも実態は政策がなかなか機能しないために問題がなかなか解決しないというのが現状となっています。
政策的には主に高齢者が長期に入院しているような療養病床をどんどん減らしていくということを言っています。
そしてこれを実行するために小泉内閣の時代に各都道府県が医療費削減のための療養病床を減らすという「計画をつくる」ということを決めて一応計画はつくりました。
ですがそのうち政権が変わり療養病床を減らす計画はやめましょうということになってしまいました。
昨今では療養病床を介護施設に変えれば入院患者の削減や医療費の削減につながるのではないかということで、新しい介護施設である「介護医療院」をつくるという政策があります。
医療提供体制における課題
このようにこの医療提供体制の問題の根本的なところは実は疾病構造の変化に制度が対応できていないというところにあります。
もちろんこのような問題は日本だけのものではありません。この考え方でより効率的な医療体制をつくろうということでヨーロッパなどはどんどん医療制度改革を進めていっています。日本も遅ればせながら少しづつ制度改革に取り組んではいますが、事実上それは感染症が撲滅されたという認識のもとにおこなわれてきました。
こういったなかで今回の新型コロナのような問題が起こるわけです。
このような現実のなか、蓋を開けてみれば感染症の隔離のための病棟がどんどん削減されてなくなってきている、感染症を検査する体制がかつてのような形ではなく検査自体ができない。という問題が明らかとなりました。
昔と比べて疾病構造が変わった…それに対応するために医療供給体制を変えなければいけない…と努力を続けてきました。
ですがその結果今回のコロナのような感染症が起こると一気に医療崩壊するというような極めて脆弱な医療提供体制になってしまったということがも新型コロナウイルスまん延によって白日のもとにさらされることとなりました。
そしてこれがまた日本の医療に対して新たな問題を提起することとなったわけです。
現在日本が置かれている現状に対して今までやってきた政策を変えるのかというと、まだそういったところに議論が行くような状況ではありません。
新型コロナウイルスに対しては現在医療職だけでなく全国民が必死で格闘しています。なので今までの政策の方向性を変えるのかというようなところにまでは話は至っていません。
まとめ
日本の医師・看護師不足や医療提供機関の不足、また長期入院の問題に関しては今回の新型コロナウイルスのまん延以前からずっと議論が続いていました。
ですが、一旦話題になって盛り上がりをみせると徐々に鎮火されていく…という問題があることをわかりながら見て見ぬふりをするという体制が今回の医療崩壊を引き起こしたのではないでしょうか。
はじめに述べたように日本には入院治療できる設備やベッドが十分にあります。ですがその大半が有事の事態に対応できるものではなくなってしまったという現状が今の日本です。
ゆっくり入院して朝昼晩たっぷりとリハビリやマッサージが受けられるという現状が今の日本の状況でいつまで継続できるのでしょうか?なぜ今自費リハビリが必要とされているのか。考えていかなければならない時期が訪れているのではないでしょうか?
参考資料

社会保障を問い直す/中央法規出版/2003.4.1/植村尚史著





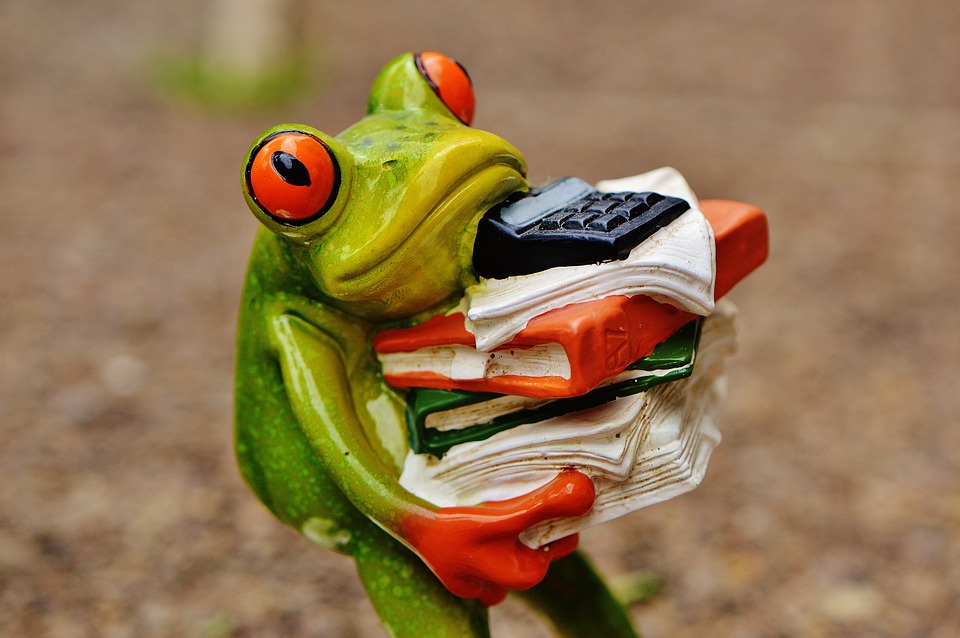
コメント